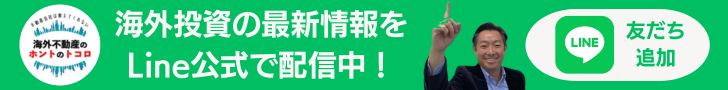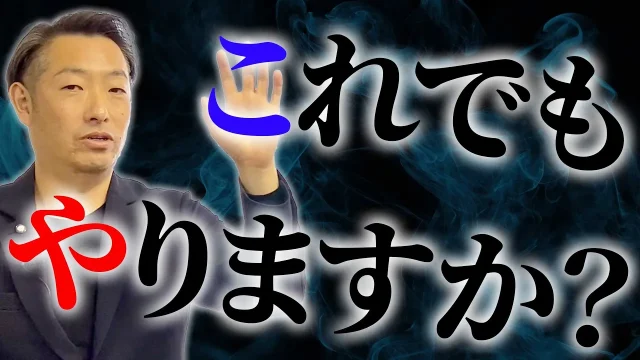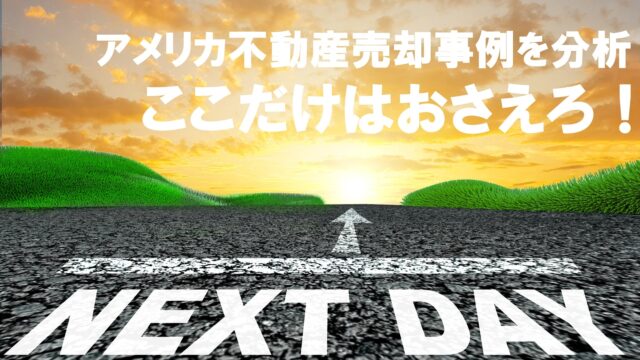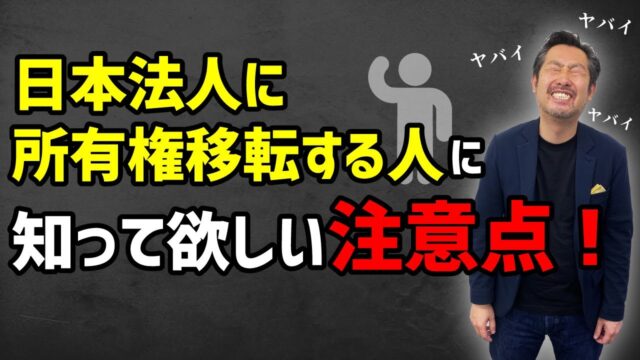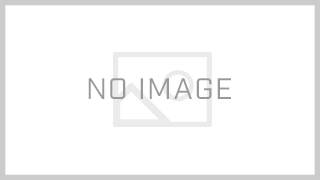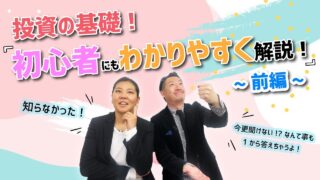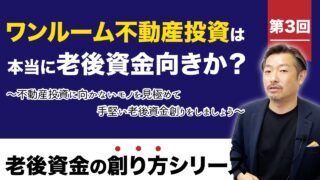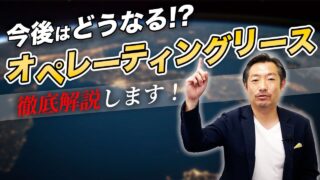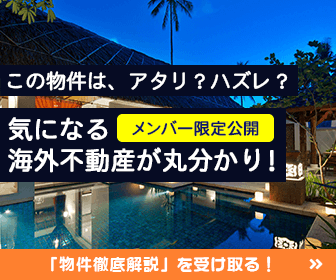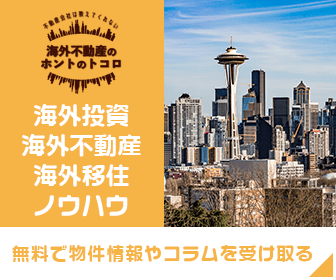海外不動産投資は、かつては一部の超富裕層や法人だけの選択肢と思われていました。しかし、今や多くの日本の富裕層が、自身の資産防衛や通貨分散、相続対策の一環として本格的に検討するテーマとなっています。その中でも「なぜアメリカ不動産が選ばれるのか」という疑問は、実務に携わる立場で必ず耳にする重要な問いです。
世界には東南アジア、ヨーロッパ、ドバイなど、魅力的な投資先が数多くあります。それでも、アメリカが多くの富裕層に選ばれるのはなぜなのか。本記事では、その理由を東南アジアや欧州、ドバイとの比較も交え、実務者視点で解説します。

1. 世界の富裕層が不動産投資に求める条件
富裕層の不動産投資における目的は、単なる高利回りやキャピタルゲインではありません。むしろ次のような条件が重要視されます。
-
通貨の分散・防衛:世界基軸通貨である米ドルやユーロ建ての資産保有
-
資産保全:強固な所有権、法制度による権利の保護
-
相続・承継戦略:長期保有による世代間資産移転のしやすさ
-
流動性:売却時や出口戦略の自由度
こうした条件をバランスよく満たす国・地域を選ぶことが、富裕層の不動産戦略の本質です。その解がアメリカ不動産にはあるのです。
2. アメリカ不動産の5つの強み
2-1. 世界最大規模のマーケットと高い流動性
アメリカ不動産市場は規模が大きく、買い手・売り手ともに厚みがあり、市場価格も比較的透明です。そのため、売却時の出口戦略が立てやすく、流動性を重視する富裕層には非常に魅力的です。
2-2. 法制度の透明性と安心感
アメリカは不動産取引に関する法律が整備され、登記制度や契約内容の明確化が徹底されています。外国人でも多くの州で自由に不動産を所有でき、権利関係が明確です。英語圏での取引という点も、契約・法務の透明性に安心感を与えています。
2-3. 米ドル資産の保有
米ドル建て資産を持つことは、円安や他国通貨リスクを回避する手段となります。富裕層が資産の一定割合をドル資産で保有する理由はここにあります。
2-4. 減価償却などの税務メリット
アメリカ不動産は減価償却による課税所得の圧縮が可能で、法人や信託と組み合わせれば承継対策も含めた節税戦略が取れます。
2-5. 多様な投資スタイル
トリプルネットリース(NNN)、Airbnb、Flip、ADU、高級住宅など、幅広い投資手法が選択できます。リスク許容度や投資目的に応じた柔軟な戦略が立てられるのも魅力です。
3. 東南アジア・ヨーロッパ・ドバイと比較して見えるアメリカ不動産の強み
アメリカ不動産が富裕層に選ばれる理由は、他の人気エリアと比べると一層鮮明になります。ここでは東南アジア、ヨーロッパ、ドバイと比較し、その違いと強みを整理します。
3-1. 投資をする通貨
アメリカ不動産の魅力の一つは、基軸通貨である米ドル建て資産を直接保有できる点です。これにより、世界的な通貨防衛の観点からも安心感があります。東南アジアでは各国通貨での資産保有となり、為替リスクの影響を大きく受けやすくなります。ドバイはディルハム(AED)建てですが、米ドルとペッグされているため比較的安定しています。ヨーロッパはユーロやポンド建てで、一定の信頼性はあるものの、米ドルほどの国際的な基軸性はありません。
3-2. 土地の所有権
所有権の自由度はアメリカが際立っています。ほとんどの州で外国人による土地・建物の自由な取得が認められています。一方、東南アジアでは多くの国で厳しい制限があります。たとえば、タイでは土地の所有は不可で、外国人はコンドミニアム全体の49%までしか保有できません。ベトナムやインドネシアでは土地は国有で、外国人は使用権のみ認められています。フィリピンでは土地所有自体が禁止され、法人経由でも現地資本比率が60%以上必要です。ヨーロッパは国によりますが、多くの国で所有が可能です。ドバイも原則所有は可能ですが、一部は長期リース権による取引となります。
3-3. 法制度と登記の信頼性
法制度の安定性と登記の信頼性では、アメリカとヨーロッパが高い評価を得ています。権利関係が明確で、外国人投資家も安心して取引ができます。ドバイも法制度は整備されていますが、政策変更のリスクが指摘されます。東南アジアは国による差が大きく、登記や権利確認でトラブルになるケースも少なくありません。
3-4. 流動性と出口戦略
出口戦略の立てやすさはアメリカの大きな強みです。市場規模が圧倒的に大きく、価格形成も透明で、売却時の買い手層も厚いため流動性が非常に高いのです。東南アジアやドバイは、買い手層が限定されることが多く、思ったように売却できないリスクがあります。
3-5. 税務メリット
税務面でもアメリカは優位性があります。特に減価償却を活用した節税効果が大きく、法人や信託を活用すればさらなる戦略の幅が広がります。ドバイは法人を活用した優遇があるものの、東南アジアは譲渡益課税や印紙税の負担が重く、税務的メリットは限定的です。
4. 規制と税制リスク|国ごとに異なる注意点と対策
アメリカ不動産のリスクとしては、売却時にFIRPTA(外国人投資家不動産税法)に基づき、譲渡価格の15%が源泉徴収されることが挙げられます。申告を経て還付されますが、資金流動性に注意が必要です。また、フロリダやテキサスなどでは外国人による農地や重要施設周辺の土地取得を制限する法規制が強化されています。
東南アジアでは税制が複雑です。タイでは取引時に印紙税や特別事業税が発生し、取引総額の5〜6%が税コストとなる場合があります。マレーシアでは不動産譲渡益税(RPGT)があり、短期保有の場合最大30%が課税されます。
こうした背景から、どの国を選ぶ場合でも、現地税理士や弁護士、日本側の専門家と連携し、二重課税防止条約の活用なども含めた正しい申告と計画が不可欠です。
5. アメリカ不動産で富裕層が築く戦略的資産運用の実例
富裕層はアメリカ不動産を単なる投資対象としてではなく、資産形成・防衛・承継の手段として戦略的に活用しています。
日本人富裕層では、LLCや信託を活用し、減価償却による課税圧縮と相続対策を両立させるスタイルが一般的です。中華系富裕層の場合は、法人や信託を組み合わせ、子女の教育や移住と連動させたスキームが取られることが多く、投資とライフプランを一体化させています。欧州や中東系の富裕層は、キャッシュでの一括購入による長期保有型の「守りの資産運用」が目立ち、資産ポートフォリオ全体の安定性を重視しています。
さらに、アメリカ不動産投資の王道といえるのが、1031 Exchange(いわゆる買替特例)を活用した資産の膨張戦略です。1031 Exchangeを使えば、売却物件の譲渡益課税を繰り延べつつ、より高額な不動産への買替が可能となり、複利的に不動産資産を拡大していくことができます。外国人投資家であっても、アメリカ法人を設立してその法人を所有主体とすることで、このスキームの恩恵を受けることができます。
このように、富裕層のアメリカ不動産投資は単なる購入や保有ではなく、税務・承継・通貨防衛・出口戦略までを包括した“構造設計”の一環として緻密に組み立てられています。
6. まとめ
アメリカ不動産は、通貨、法制度、流動性、税務メリット、投資商品の多様性といった多角的な強みを持っています。特に富裕層が求める「資産の守りと攻めを両立させる投資対象」として、依然としてトップクラスの選択肢であり続けているのです。
東南アジア、ヨーロッパ、ドバイなども投資先として魅力はありますが、規制、税務、流動性、出口戦略の面でアメリカほどの総合力を持つ地域は多くありません。
単なる利回りや短期のキャピタルゲインにとどまらず、長期的な資産防衛と承継の視点から、アメリカ不動産をどう位置付け、どのように持つか─その構造設計こそが、富裕層にとって最も重要なテーマといえるでしょう。
ご興味がある方はお問合せください。
▼お問い合わせはこちら
▼こちらの動画をあわせてご覧ください!
海外不動産のホントのトコロYouTube版
記事では書ききれないリアルを発信中!
個別に相談したい方はこちら!