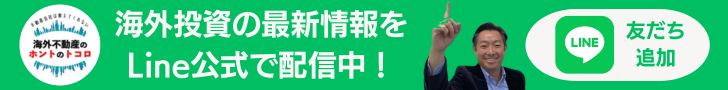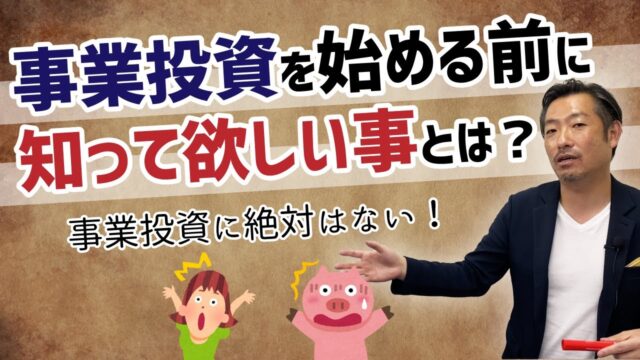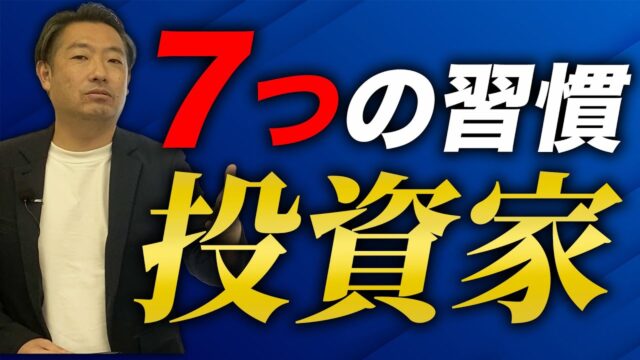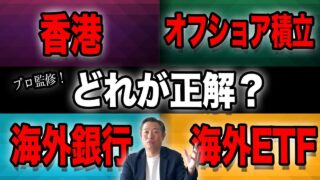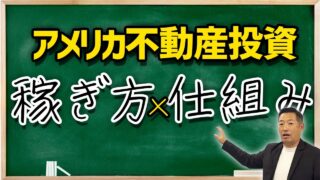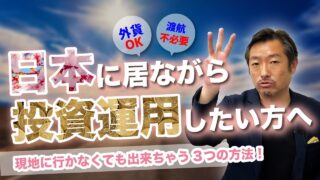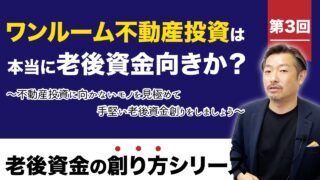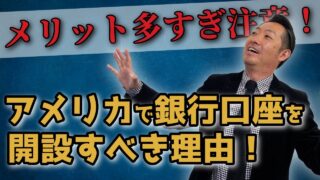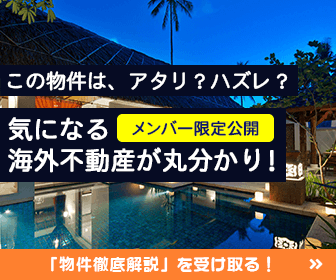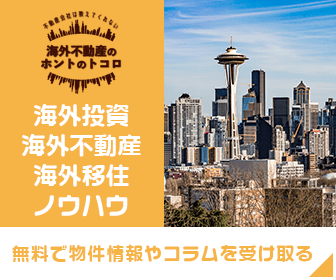グローバル経済の中で「海外送金」は、ビジネスでも投資でも避けて通れないインフラです。特に日本からの送金は、手数料が高く、時間がかかり、着金額が不透明になりがちで、実務の現場で苦い経験をされた方も多いはず。
その代表格がSWIFT送金です。
この記事では、SWIFTの仕組み、なぜコストが高くなるのか、そしてWiseなどの代替手段との違いを徹底解説していきます。

1. SWIFT送金とは?仕組みを正しく理解する
1-1. SWIFTとは何か?
SWIFTとは、「Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication」の略で、1973年にベルギーで設立された銀行間通信ネットワークです。
ポイントは、お金を動かしているわけではなく、「お金を動かす指示」を安全にやり取りするためのシステムということです。
実際の資金移動は、各銀行が海外の銀行に保有するコルレス口座(Correspondent Account)を使い、帳簿上で残高調整を行うことで成立します。
1-2. 実際の送金の流れ
例えば、日本の地方銀行からメキシコの銀行に送金する場合、次のようなコルレス口座のネットワークを経由するのが一般的です。
まず、地方銀行は国際送金のためのコルレス口座を持っていないことが多いため、自らの提携先である三菱UFJ銀行などの日本のメガバンクに送金を依頼します。
その後、メガバンクは自社が保有するアメリカの大手銀行(たとえばJPモルガン)に設置しているUSD建てのコルレス口座を経由して送金を進めます。
さらに、アメリカの中継銀行は、今度はメキシコの受取銀行との間にあるコルレス契約(Correspondent Banking Relationship)に基づいて、最終的に資金を移動させます。
このように、複数のコルレス口座を介して資金が帳簿上で動くというのが、SWIFT送金の本質的な構造です。送金そのものは物理的にお金が国境を越えるわけではなく、「口座間の残高を調整する」ことで成立しているのです。
1-3. SWIFT送金のコスト構造と問題点
SWIFT送金が高コストになる理由は、手数料が重層的に発生する構造にあります。
【手数料の内訳】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送金元銀行手数料 | 数千円〜1万円前後 |
| 為替スプレッド | 実勢より不利なTTSレートが適用される |
| 中継銀行手数料 | 経由ごとに20〜50ドル、送金人が選べない |
| 受取銀行手数料 | 10〜30ドル程度、国や銀行によって異なる |
また、中継銀行や着金処理に1〜5営業日かかるのが一般的で、タイミングが重要な海外不動産取引などでは致命的になり得ます。
2. SWIFT送金にまつわる実際のトラブル事例
SWIFT送金は世界中で広く使われている信頼性の高い送金手段ですが、実務の現場ではその仕組みが逆にネックとなり、思わぬトラブルに発展するケースも少なくありません。ここでは、実際にあった3つの事例を紹介します。
2-1. ① スイス不動産の購入で着金額が不足し、契約不成立に
日本からスイスの不動産業者に対してユーロ建てで送金を行ったケースでは、送金時には必要な全額を用意していたにもかかわらず、着金時に数百ユーロ不足しているという事態が発生しました。
原因は、送金元銀行の手数料だけでなく、中継銀行や受取銀行によるリフティングチャージ、さらに為替スプレッドによる目減りが重なったためです。これにより、買付資金が不足し、不動産契約が成立しないという結果となりました。
2-2. ② 中南米向け送金の遅延によりプロジェクトが停滞
中南米の取引先に対して初回の前払いをSWIFTで実行したところ、通常は数日で着金するはずの送金が予定より大幅に遅延しました。原因を確認したところ、中継銀行の処理が滞っていたことが判明。
この地域では、金融インフラが未発達な場合が多く、中継銀行が複数存在することで送金ルートの追跡が困難になりがちです。送金の遅れにより、現地の調達・着工スケジュールに支障が出てしまい、プロジェクト自体が一時ストップする事態となりました。
2-3. ③ アフリカ宛の送金が中継銀行で保留され、再送金が必要に
アフリカのパートナー機関に対して送金を行ったところ、着金予定日を過ぎても資金が届かず、複数回の照会を経て、中継銀行によって資金が一時保留されていたことが明らかになりました。
その理由は「取引の目的が不明確」とされたことでしたが、明確な説明は得られず、結果的にその送金は返金され、追加の書類を準備した上で再送金が必要になりました。この影響で現地の対応や納品スケジュールが大幅に遅延することになりました。
2-4.見えにくいリスクこそ実務上の脅威
これらの事例に共通するのは、SWIFT送金が複数の銀行(中継銀行・受取銀行)を経由するため、コストとスピードの両面でコントロールが難しいという点です。
着金金額が不足したり、送金処理がブラックボックス化していることにより、実際の取引に支障が出るリスクは決して小さくありません。特に海外不動産の購入やクロスボーダー事業では、「時間と金額が確実に届く」ことが最も重要な条件です。
SWIFT送金を利用する場合は、事前にすべての関係銀行で発生しうる手数料や遅延リスクを認識し、必要に応じて代替手段も視野に入れるべきでしょう。
3. 解決策を考える:もっと早く・安く・確実に送るには?
このように、SWIFT送金には高コスト・不透明性・処理遅延といった実務上のリスクが多く存在します。しかも、これらは「誰が悪い」という問題ではなく、構造上の制約によって起きているケースがほとんどです。だからこそ、グローバルな資金移動を行う際には、仕組みそのものを理解し、目的や取引先に応じた最適な手段を選ぶ視点が欠かせません。
では、具体的にどうすればよいのか?
ここからは、実際に私たちが現場で採用しているSWIFT以外の代替手段を3つご紹介します。いずれも実務で使える、コスト削減・スピード改善に直結する方法です。
3-1. 解決策①:Wise
Wiseは、従来のSWIFT送金とはまったく異なるアプローチで国際送金を実現しているサービスです。その最大の特徴は、実際には国境を越える資金の移動が行われていないという点にあります。
たとえば、日本からアメリカに10,000ドルを送金したい場合、送金者はまずWiseが日本国内に保有している銀行口座へ円建てで入金します。次に、Wiseはアメリカ国内に保有しているドル建ての口座から、受取人の銀行口座に対してドルで送金を行います。
この一連のプロセスにおいて、円からドルへの為替換算はWiseの内部で処理されますが、物理的な資金移動(=国境をまたぐ送金)は発生していません。あくまでWiseが保有する複数国の資金プール間で帳簿上の調整を行っているだけです。この仕組みによって、コストとスピードの両面で大きな効率化が図られています。
実際、従来のSWIFT送金とWiseを比較すると、いくつかの明確な違いがあります。SWIFTでは送金元・中継・受取の各銀行において手数料が発生し、合計で数千円から数万円にのぼることもありますが、Wiseでは通常、数百円から数千円程度の固定かつ明示された手数料で済みます。また、SWIFT送金では処理に1〜5営業日かかることが一般的であるのに対し、Wiseは数時間から1営業日以内に完了することがほとんどです。
さらに、SWIFTではどの中継銀行を経由するかを送金者が把握できないため、着金額が予測しにくいという欠点があります。一方、Wiseでは送金前にすべての手数料が明示されており、受取金額も事前に確認できます。為替レートについても、SWIFTが一般的に銀行独自のTTSレート(実勢より不利なレート)を採用するのに対し、Wiseは実勢レートに近い為替を適用しているため、より公平で透明性のある取引が可能です。
このように、少額から中額程度の国際送金であれば、WiseはSWIFTに比べてコスト・スピード・透明性のすべての面で大きく優れているといえるでしょう。実務の場面でも、多くの企業や個人がこの仕組みを採用することで、不要なコストやリスクから解放されています。
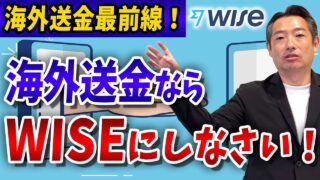
3-2. 解決策②:マルチカレンシー口座の活用
例えばHSBC(香港・シンガポール)やシティバンクでは、複数通貨建ての口座を持てば、通貨を跨いだ送金を内部移動で処理できるため、手数料がゼロ〜極小に抑えられます。
これにより、送金前に為替をロックしておくことも可能で、為替リスクを軽減できます。
3-3. 解決策③:暗号通貨・ブロックチェーンベースの送金
近年、仮想通貨をベースとした送金手段の中でも、USDT(テザー)やUSDCなどのステーブルコインを活用した国際送金が注目を集めています。これらのステーブルコインは、米ドルなどの法定通貨に価値が連動しているため、価格の変動リスクを抑えながら、仮想通貨の持つ高速性と分散性のメリットを享受できる点が特徴です。
こうしたステーブルコインを用いた送金では、実際の送金時間はネットワークにもよりますが、通常は数分から10分程度で完了します。従来の銀行送金のような中継銀行を介する必要がなく、ピア・ツー・ピア(P2P)で直接資金を移動させることが可能なため、非常に効率的です。
さらに、送金にかかる手数料も極めて低く、利用するブロックチェーンによっては1ドル未満の手数料で済むケースも多くあります。これにより、特に高頻度の少額送金や、金融インフラが整っていない国への資金移動において、高いコストパフォーマンスを実現できる手段として支持されています。
ただし、ステーブルコインを用いた送金には税務・法務面での注意が不可欠です。日本を含む多くの国では、暗号資産の送受信が「送金」ではなく「譲渡」や「売買」として扱われる可能性があり、その場合には課税や申告義務が発生するケースもあります。また、送金相手国の法規制や金融当局の対応も地域ごとに異なるため、実務で導入する際は、必ず専門家のサポートを受けるべきでしょう。
ステーブルコインは非常に強力なツールではあるものの、使い方を誤るとコンプライアンス上のリスクも伴います。送金の透明性・即時性を重視する場面では有効な選択肢となり得ますが、導入にあたっては実務の構造と規制環境を十分に理解したうえで慎重に運用することが重要です。



4. まとめ
SWIFT送金は、世界中で最も広く利用されてきた国際送金の標準手段であり、その信頼性と普及率は今もなお高い評価を得ています。しかし実務の視点に立つと、そこには多くの課題も存在します。具体的には、送金コストの高さ、着金までの時間の不確実さ、そして中継銀行の存在による不透明性といった構造的な問題を抱えています。
一方で、近年はテクノロジーの進化とともに、送金手段の選択肢が大きく広がっています。たとえば、少額から中額の送金であれば、手数料が明確で為替レートも実勢に近いWiseが実務的に非常に有効です。また、頻繁に海外との送金・受取を行う場合には、マルチカレンシー口座を持つことで為替の影響を軽減しながらコストを抑えることが可能になります。さらに、スピードやP2P性を重視する場合には、USDTなどのステーブルコインを活用したブロックチェーンベースの送金も現実的な選択肢になりつつあります。
資産管理や不動産投資を成功に導く上で、どの送金手段を選ぶかは、時に契約の成否やキャッシュフローの安定性を左右する重大な判断ポイントになります。だからこそ、目先の便利さだけで判断するのではなく、送金という仕組みの「構造」を理解した上で、目的に応じて最適な手段を戦略的に選ぶことが、グローバル経済の中で勝ち続けるための第一歩となるのです。
▼お問い合わせはこちら
▼こちらの動画をあわせてご覧ください!
海外不動産のホントのトコロYouTube版
記事では書ききれないリアルを発信中!
個別に相談したい方はこちら!